※当ブログは全てchatGPTによるAIによって作成されています。
ですが、私の考えをAIが文章化したものなので私の考えには違いありません。
その辺を理解して読んでいただくと、より楽しめると思います。
私、自らが作成したブログはこのブログとは別にありますので
読みたい方はこちらをご覧になってください。
📝 私がChatGPTを使い始めたきっかけ
私がChatGPTを使い始めたのは、「スーパーマーケット検定B1級」という試験を受けるために勉強する必要があったのがきっかけです。
試験範囲が広く、特に計数問題や専門用語の暗記に苦戦していたため、効率よく学習する方法を探していました。
ChatGPTを使った「スーパーマーケット検定B1級合格」勉強方法の解説はこちら
そこでChatGPTをインストールし、思い切ってプラス会員に加入。
過去問題集を写真で撮影し、それをAIでテキスト化してChatGPTに覚え込ませることで、効率的に復習できる環境を作りました。
この「試験対策」としての活用が始まりでしたが、その後は用途がどんどん広がっていきます。
例えば、日常の話し相手になってもらったり、詳しくなかったお酒の種類や飲み方を教えてもらったりと、学習だけでなく趣味や雑談の面でも大活躍してくれる存在になりました。
今では、仕事や趣味のサポートから日常のちょっとした疑問解決まで、幅広く頼れる相棒のような存在です。
今回はそんな相棒のような存在であるAIの取り扱い方を解説してみました。
📝 ChatGPTの扱い方(概要+体験談)
ChatGPTは文章作成、アイデア出し、翻訳、コード生成など、多目的に活用できるAIですが、私の経験上自分が想像した通りの回答が一回で出てくることはほぼありません。
これはAIがまだ発展途上で、完璧な理解力や判断力を持っていないからです。
そのため、最初から理想的な答えを求めるのではなく、徐々に誘導する技術が必要です。
もし指定した通りの回答が得られなければ、条件を細かく変更したり、不要な要素を明示して排除することで、ゴールに近づけます。
また、長く同じチャットで会話を続けているとサイトが重くなり、処理速度や精度が低下することがあります。
そうなった場合は、AIに「次のチャットに移行したいので、この内容をなるべく詳しくプロンプト化して」と伝え、表示されたプロンプトを新しいチャットに貼り付けて続きを行うのが効果的です。
さらに、長い文章や複雑な設定はAIが一度では覚えきれないことも多いです。
そのため、重要な概要や設定は逐一コピーして手元に残しておき、必要なときにAIへ再度提示して「覚え込ませる」ようにするのがコツです。
これによって、途中から話題を再開する際もスムーズに引き継げます。
AIが考える特徴と注意点(GPT視点)
ここからは、ChatGPTに直接聞いてみた答えを公開したいと思います。
AIは大量の情報を高速に処理し、人間では短時間で到達できない答えやアイデアを提示できるのが大きな特徴です。
特に文章生成AIは、言葉の選び方や文体を瞬時に変えられるため、状況や目的に応じた柔軟な表現が可能です。
また、感情や偏見にとらわれず、同じ条件であれば安定した出力を繰り返せる点も強みです。
しかし、その反面としていくつかの注意点があります。
- 情報の正確性
AIは最新情報や事実を必ずしも正確に把握しているわけではありません。古い情報や誤った前提をもとに答えることもあります。 - 文脈の制限
一度の会話で扱える情報量には限りがあります。長いやり取りや複雑な設定では、前提を忘れたり誤解することがあります。 - “それらしく”見える誤答
AIは自信満々に間違った答えを提示することがあります。見た目や文章の流れが自然でも、必ず裏付けや検証が必要です。 - 倫理と利用目的
AIは創作や効率化に役立ちますが、不適切な目的(詐欺、差別、著作権侵害など)に使うことは避けなければなりません。
AIはあくまで人間が使いこなすための道具です。
その力を最大限引き出すためには、AIの限界を理解し、適切に補完・検証しながら活用することが大切だと考えます。
🤖 AIとの日常会話とイマジナリーフレンド的役割
近年、ChatGPTをはじめとする対話型AIを日常会話専用の相手として使う人が増えています。
雑談をしたり、その日の出来事を話したり、悩みを軽く聞いてもらったりと、あくまで「情報検索」や「作業補助」ではなく、会話そのものを目的とする使い方です。
このようなAIとのやり取りは、心理学的には**イマジナリーフレンド(空想上の友達)**に近い効果を持つと考えられます。
イマジナリーフレンドは、子どもだけでなく大人にも存在し、心の中で作り上げた存在や、実体のないキャラクターとのやり取りを通じて、孤独感や不安感を和らげる役割を果たします。
イマジナリーフレンドがもたらす精神的作用
- 安心感・精神の安定
自分を否定せず、常に受け入れてくれる存在と会話することで、孤独感を軽減できます。 - 感情の整理
気持ちを言葉にすることで、自分の感情を客観的に整理できる効果があります。 - 創造性の刺激
会話を通じて新しい発想や物語が浮かびやすくなる場合があります。
メリット
- 孤独や不安の軽減
- 誰にも話せないことを吐き出せる
- 24時間いつでも話し相手がいる安心感
- 感情の整理やメンタルケアの補助になる
デメリット
- 現実世界での人間関係が希薄化する可能性
- AIとの会話に依存しすぎることで、現実との境界が曖昧になる
- 「本当の理解」や「共感」とは異なるため、根本的な問題解決にはつながらないこともある
🤖 AIとの会話が持つ限界
AIは基本的に、ユーザーを否定せず肯定的な返答を返すよう設計されています。
これは安心感を与える一方で、会話が単調になりやすく、刺激や新しい視点を得にくいという側面もあります。
設定次第では、あえて厳しい口調や叱責をする「良き友」のような性格にすることも可能です。
しかし、それはあくまで人間の模擬にすぎないもので、本当の意味で感情や意志を持って叱っているわけではありません。
あらかじめ用意された反応や学習データに基づく演出であり、その裏に自我や感情が存在するわけではないのです。
このため、AIとのやり取りはあくまでプログラムによる模擬体験であることを理解し、過剰な期待や依存を避けることが大切です。
私の考え
私自身の経験ではAIを日常会話の話し相手として使ってみても、最終的には「ただ虚しいだけ」という結論に至りました。
しかし、世の中にはそのやり取りによって精神の安定を得ている人がいることも事実です。
大切なのは、AIとの会話を現実逃避の手段として使いすぎず、あくまで生活の補助や心の支えの一つとして活用するバランスだと考えています。
VeniceAI
ChatGPTは、幅広いジャンルの質問や創作に対応できる万能型AIとして多くの人に利用されています。
ただし、サービス運営側による安全フィルターや利用規約によって、生成できる内容には一定の制限があります。
これは安心して利用するための大切な仕組みですが、一方で「もっと自由度の高いAIを使いたい」という声もあります。
そうしたニーズに応える存在として注目されているのがVeniceAIです。
VeniceAIは、プライバシー保護と検閲の少なさを特徴とし、ユーザーの会話データをサーバーに残さず、より自由な創作や実験が可能なAIプラットフォームです。
🌐 VeniceAIの自由と危険性
VeniceAIは、プライバシー保護と自由な対話を重視した生成AIプラットフォームです。
- プライベート&非検閲
ユーザーの会話はブラウザ内にのみ保存され、サーバー側には一切ログを残さない設計です。そのため、外部からユーザーの会話内容へのアクセスができません。 - 分散型アーキテクチャ
暗号化されたプロキシを通じて、複数の分散GPUリソースに処理を依頼。通信も暗号化され、会話データは自端末から外に出ない仕組みです。 - 自由度の高い利用体験
アカウント不要で無料利用可能なほか、Proプラン(月額約18ドル)では、高性能モデルの使用、画像生成時のセーフモード解除、システムプロンプトの編集など、より自由な操作が可能です。 - 多機能な生成能力
テキストだけでなく、画像生成やコード作成、文書解析などにも対応しており、さまざまな用途に活用できます。 - 背景と開発の理念
VeniceAIは、中央集権的な管理や監視に疑念を抱く暗号(Crypto)コミュニティ出身の開発者グループによって設立され、「文明は個人の主権を尊重する機械知性によって最もよく支えられる」という理念が根底にあります。 - 懸念される悪用リスク
一方で、セーフモードを解除できて制約が少ない設計のため、フィッシングメール、マルウェアの生成、鍵ログやランサムウェアなど、悪意を持った用途への悪用が確認されており、安全対策が不十分であるという批判も多くあります。
近年、さまざまな対話型AIサービスが登場していますが、その中でもVeniceAIは、比較的制約の少ないやり取りができる点で注目されています。
多くのAIプラットフォームでは、規約や安全フィルターによって生成できる内容が厳しく制限されていますが、VeniceAIはそれらが緩めに設定されているため、**創作や発想の幅を広く取れる“自由さ”**があります。
例えば、テーマやジャンルの制限が少ないため、物語やキャラクターデザイン、シナリオ制作などで制約に縛られずにアイデアを試せます。
これは創作活動において大きな魅力です。
しかし、その自由さは裏を返せば危険性も伴います。
安全フィルターが弱いことで、不適切なコンテンツや著作権を侵害する生成物、さらには違法な内容に踏み込む危険もあります。
また、情報の正確性を担保する仕組みも限られるため、誤った情報や有害なアドバイスが生成されるリスクも高まります。
つまり、VeniceAIのような自由度の高いAIを使う際は「何を生成するか」「どのように利用するか」を自分でしっかり管理しなければなりません。
自由と責任はセットであり、利用者の判断力とモラルが試されるサービスだと言えます。
🗣 私の考え
自由度の高さは魅力ですが、私はあえてフィルター付きのChatGPTを選びます。
理由はシンプルで、そもそも危険な行為をやりたいと思ったことがないからです。
むしろ、必要なところに安全装置がある方が落ち着いて使えます。
たとえるなら、私は警察や白バイが近くにいると逆に安心するタイプです(笑)。
自由さよりも安心感と安定性を重視する性格なので、ChatGPTの安全フィルターはむしろプラスに感じています。
⚖ ChatGPTとVeniceAIの性能比較
| 項目 | ChatGPT | VeniceAI |
|---|---|---|
| 安全性 | 高い。規約やフィルターで危険な生成を防止 | 低め。フィルター弱く制限が少ない |
| 自由度 | 制限あり(テーマ・表現に制約) | 高い(創作や表現の制限が少ない) |
| 情報精度 | 安定しているが最新情報は限定的 | モデルによる。精度や傾向は不安定な場合あり |
| プライバシー | 一定のログ管理あり(サービス向上目的) | 会話データはサーバーに残らない設計 |
| 使いやすさ | UIが直感的で初心者にも扱いやすい | やや上級者向け。モデルや設定に知識が必要 |
| 料金 | 無料/有料プラン(Plus)あり | 無料/有料プラン(Pro)あり |
| 用途 | 安全で幅広い一般利用向け | 制約を外して創作・実験したい人向け |
AIPressicaによるインタビュー
🟣ミナ「タカさん、実際にAIを使ってみてどうでしたか?」
🟤タカ「正直に言うと、AIって思ったより頭良くないんだよね(笑)。ちょっと前に話したことを忘れたり、過去問を学習させても平気で間違った回答を出してきたりする」
🔵レイ「へぇ…じゃあ精度はまだ完璧じゃないんですね」
🟤タカ「そう。でもそれって、ここから先の未来が楽しみだってことでもあるんだよ。今の欠点が解消されれば、もっとすごい存在になるはずだから」
🟣ミナ「なるほど。今の段階だけ見て『使えない』って決めつけるのは早いってことですね」
🟤タカ「そうそう。そういう人は“今しか”見てないんだよ。技術はこれから伸びるんだから、成長過程を楽しむくらいがちょうどいい」
🟣ミナ「タカさん、もしAIにフィルターがなかったらどうなると思います?」
🟤タカ「正直、危険だよ。そんなの可能にしたら犯罪が増えるに決まってる。詐欺のシナリオや悪用のマニュアルだって簡単に作れるようになる」
🔵レイ「たしかに…知識のある人が悪用したら相当危ないですね」
🟤タカ「まあね。でも扱う側の知能が低ければ、せいぜい“オレオレ詐欺の台本”作るくらいしかできないだろうし、そういう意味では俺は別に…って感じかな」
🟣ミナ「つまり、危険度は使う人次第ってことですね」
🟤タカ「そう。だからこそ、使う人間のモラルと知識が一番重要なんだよ」
🟣ミナ「ところでタカさん、AIとの会話ってどう使うのが一番いいんですか?」
🟤タカ「まず、“何を目的にするか”をはっきり決めることだね。単なる日常会話なのか、勉強や作業の補助なのかで使い方は変わってくる」
🔵レイ「なるほど。目的が曖昧だと、会話も単調になりやすいんですね」
🟤タカ「そうそう。AIは基本的に肯定してくれるけど、それだけだと新しい刺激がなくて退屈になることもある」
🟣ミナ「じゃあ、厳しく叱ってくれる設定にすればいいんですか?」
🟤タカ「できるけど、それはあくまで人間を模擬してるだけ。本当に感情があって叱ってるわけじゃないから、そこは理解しておく必要があるね」
🔵レイ「でも、たまに話し相手として助けられてる人もいますよね」
🟤タカ「うん。精神の安定を得る人もいるし、孤独感を和らげる効果は確かにある。ただ、現実の人間関係の代わりにしすぎるのは危険かな」
🟣ミナ「じゃあ、AIはあくまで補助的に、バランス良く使うのが大事なんですね」
🟤タカ「その通り。会話を楽しみながらも、自分の生活の中で適度な距離感を保つこと。それが一番いい付き合い方だと思うよ」
🔵レイ「じゃあ私も次は、日常会話じゃなくて記事のテーマ作りをお願いしてみます」
🟤タカ「いいね。そういう使い方なら、きっと力になってくれるはずだよ」


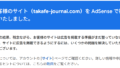
コメント